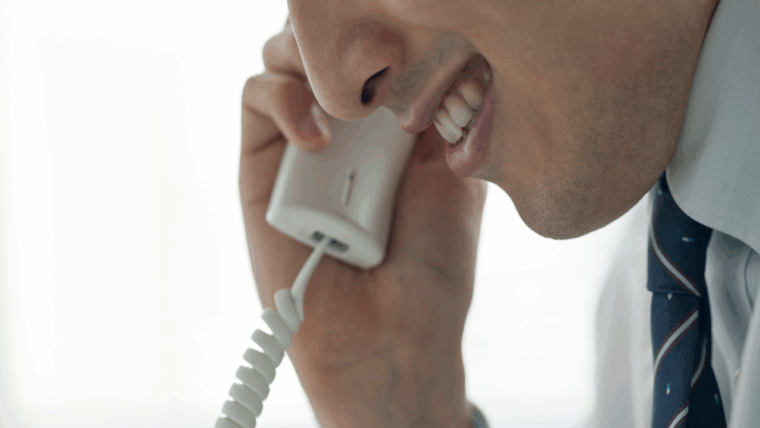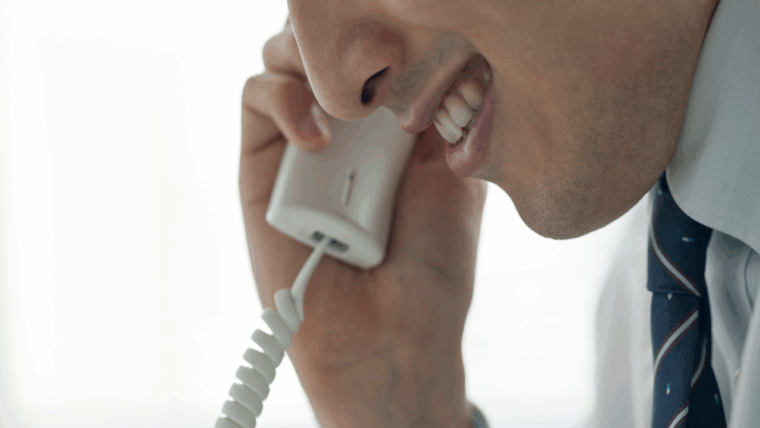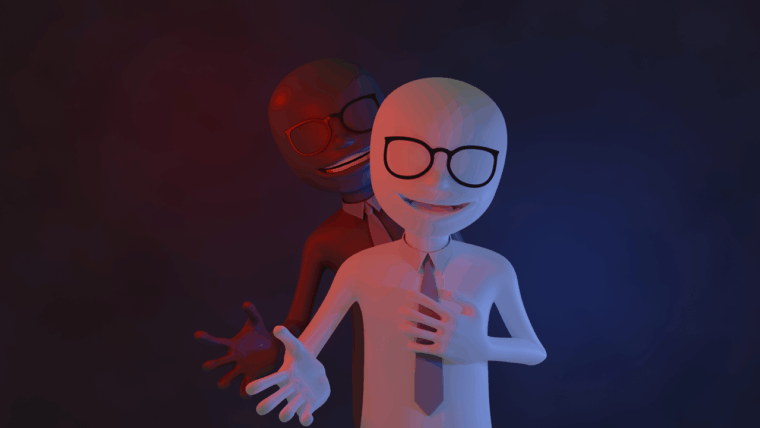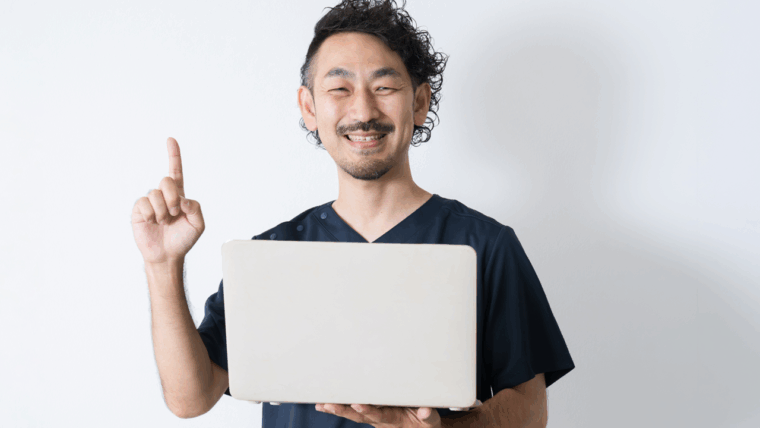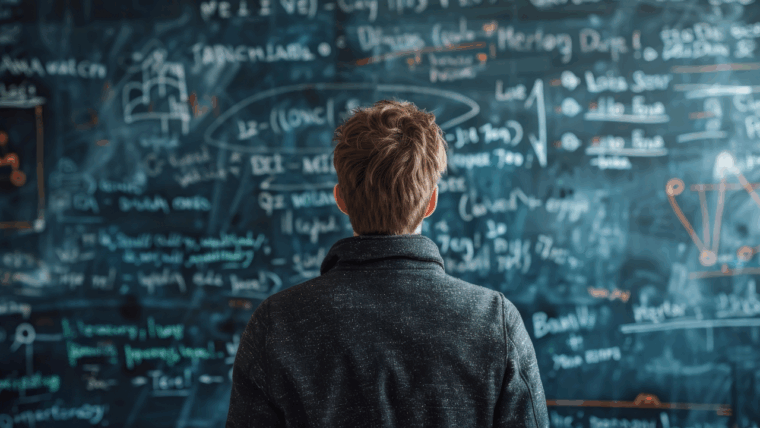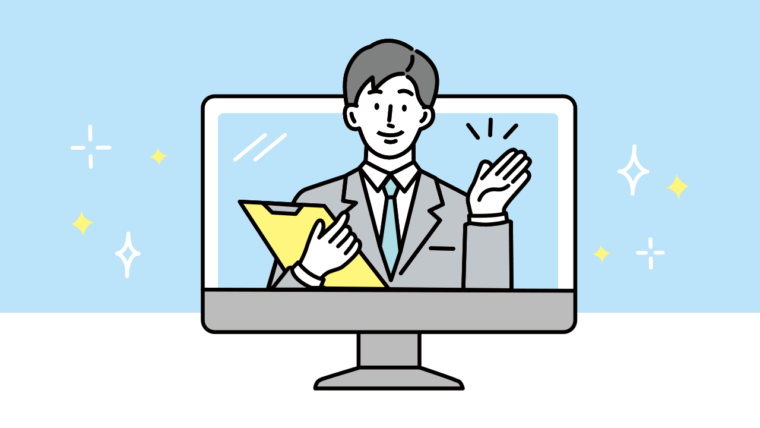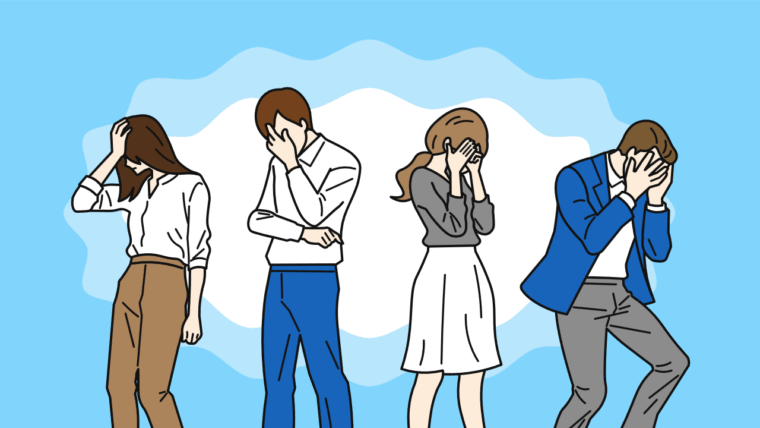ARCHIVES
コラム
-
騙される前に知っておきたい!悪質なSEO業者の手口と見抜き方
-
ホームページ制作で失敗する企業の共通点とは?実例から学ぶ対策完全ガイド
-
Google検索されない原因を完全解決!プロが教えるインデックス&SEO対策
-
なぜSEOで順位が上がらない?初心者でもできる13の改善策【2025年版】
-
「誰に頼むか」で8割決まる!失敗しないホームページ制作会社の選び方
-
悪徳業者に注意!ホームページ作成で失敗しない5つのポイント
-
MEOは意味ない…その違和感、正しいです【でも伸ばせます】
-
ホームページから集客できない原因とは?問い合わせが増える改善ステップ【初心者OK】
-
ホームページから問い合わせが来ない人へ。改善するのは“たった一つの原因”だけ
-
ローカルSEOとMEOの違いを整理。Googleマップだけに頼らない集客の考え方
-
ローカルSEOのメリット・デメリット!地域で選ばれる会社のブランディング戦略
-
SEOは広告ではない!オンラインでの信頼性をあげる方法
-
「市区町村」か「駅名」か。ローカルSEOの地域キーワードは絞り込め。
-
ホームページを”24時間働く営業マン”に育てるには?
-
なぜ「Amazon/楽天」は、いつも検索の一番上に出てくるのだろう?
-
やってはいけないSEO10選!順位が下がるNG行為とは?
-
SEO対策は意味ない?9割が誤解している”SEOが必要”な…
-
「独自ドメイン必要ない」は損してる。ドメインを取得するメリットとは?