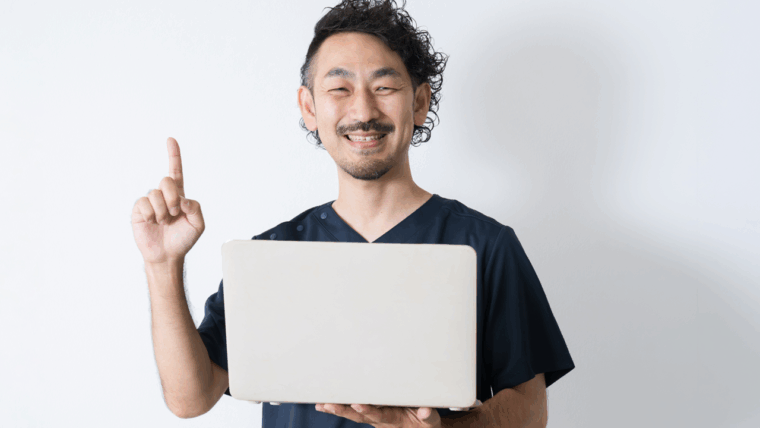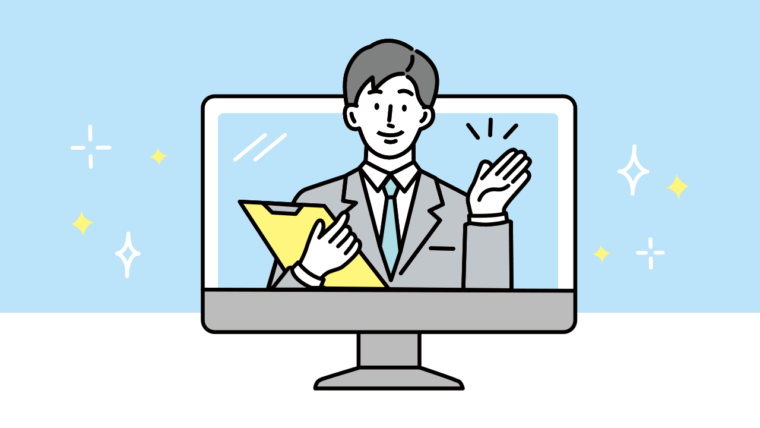「これだけやったのに、なぜ順位が上がらないんだろう…」
「業者に頼んでも変わらないし、自分でやるしかないのか?」
SEOに取り組む多くの人が、そんな壁にぶつかります。特に、検索しても答えが見つからず、不安や焦りだけが募っていくとしたら、なおさら苦しいもの。
この記事では、そんなあなたのために、
- なぜ順位が上がらないのか
- どんな改善策があるのか
- 初心者でもできることは何か
を、順を追って整理しました。
本記事では「誰にでもできる」「でも、やるべきことは明確」そう思ってもらえる構成になっています。ぜひ最後までご覧いただき、順位改善にお役立てください。
SEO順位が上がらない本当の理由は「E-E-A-T」にある
SEOの成果が出ない大きな原因は、Googleの評価軸に合っていないこと。特に近年、Googleが重視しているのが「E-E-A-T」と呼ばれる4つの評価指標です。
- Experience(サイト体験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
では、どんな状態だと評価が下がるのか、それぞれ見ていきましょう。
体験(Experience)が不足しているとは?
体験とは「訪問者がどれだけ快適に情報にたどり着けるか、どれだけ使いやすいと感じるか」という評価軸です。「見にくい」「使いにくい」と感じるサイトは、Googleからユーザー体験が悪いと判断され、順位が上がりにくくなります。つまり、「読み手のことを考えていないホームページ」は評価されません。
【よくある原因】
- 書かれてる内容が、よくわからない
- どこを見れば欲しい情報があるか分からない
- ページが重く、なかなか表示されない
- 文字が小さい、指で操作しにくい
専門性(Expertise)が不足しているとは?
専門性とは「その情報を発信している人が、その分野にどれだけ詳しいか、どんな知識や経験を持っているか」という指標です。
誰が書いているのか、どんな経験や知識を持っているのかが不明瞭な場合、Googleから「専門性がない」と判断されます。特に、医療・法律・お金に関する分野では、専門性の低い情報は上位に上がりにくくなっています。
【よくある原因】
- 筆者のプロフィールや事業実績が明記されていない
- 専門知識に基づいた深掘り解説が不足している
- 他記事との差別化となる独自の視点・経験がない
権威性(Authoritativeness)が弱いとは?
権威性とは「そのサイト(人・企業)が業界内でどれだけ認められているか」という指標です。
自分で「専門です」「経験があります」と言うだけでは不十分で、第三者からの評価や紹介が重要になります。つまり、まわりから信頼され、支持されている実績があるかどうかが、検索順位にも大きく影響してくるのです。
【よくある原因】
- 他サイトやブログからリンクが貼られていない
- SNSや口コミで言及されていない
- メディア実績、専門機関とのつながりが明示されていない
- 事例紹介やお客様の声などが掲載されていない
信頼性(Trustworthiness)に欠けているとは?
信頼性とは「そのサイトや運営者が、どれだけ安心して情報を任せられる存在か」という基準です。
会社概要や料金表示が曖昧、誤字脱字が多い、最新情報が更新されていない──こうした要因があると、訪問者は「このサイトは信用できるのか?」と不安に感じます。その結果、Googleも評価を下げる傾向にあります。
【よくある原因】
- 運営情報(会社概要・代表者・住所・電話番号)が明記されていない
- 誤字脱字が多く、定期的な情報更新がない
- 料金体系やサービス内容が曖昧
- 法的表示(プライバシーポリシー・特商法表示など)がない
初心者でも実践できる、SEO改善の具体策【全13項目】

E-E-A-Tの観点から、実際にどう改善していけばいいのか?ここでは、難易度別(★☆☆〜★★★)に具体的な13の対策を紹介します。
難易度:低
- 誤字脱字の修正、正確な情報の更新を行う(Trust)
- 運営会社情報、所在地、代表者名を明記する(Trust)
- 記事の中に「なぜこの情報が信頼できるのか」を明示する(Expertise, Trust)
難易度:中
- サイトの更新日・記事の著者名を表示する(Expertise, Trust)
- グローバルナビやフッターに信頼情報(プライバシーポリシー等)を設置(Trust)
- 読みやすい構成やデザインでユーザビリティを高める(Experience)
- よくある質問(FAQ)や業界の基礎知識ページを充実させる(Expertise)
- サイト全体にSSL(https)を導入する(Trust)
難易度:高
- クローラビリティの確保(サイトマップ送信、モバイル対応、構造化データ)(Expertise)
- SNSでの話題性や第三者による言及を促す(Authoritativeness)
- メディア掲載実績や公的機関との連携を示す(Authoritativeness)
- 高品質な被リンクを獲得する(Authoritativeness)
- 体験ベースの具体的なエピソードや事例を記事に盛り込む(Experience)
具体的な内容について解説しますね。
難易度:低(1ヶ月以内)
誤字脱字の修正、正確な情報の更新を行う
情報に誤りがあると、それだけで信頼性が損なわれます。しかし誤字脱字は、人間の目視チェックでは防げません。以下のようなツール活用し、より正確な情報提供を行いましょう
- Wordの校閲機能
- AIによる文章校正
運営会社情報、所在地、代表者名を明記する
ユーザーにとって「この情報は誰が出しているのか?」が分からないサイトは不安を感じさせます。Googleも「誰が発信しているか(誰の責任で提供されているか)」を重要な評価ポイントとして見ています。以下のような情報は、信頼性を高めるために明記しておきましょう。
- 運営者名(法人であれば代表者名も)
- 所在地や連絡先(電話番号・メールアドレスなど)
- 法的表示(プライバシーポリシーや特商法に基づく表示など)
記事の中に「なぜこの情報が信頼できるのか」を明示する
ユーザーもGoogleも、「それが本当に信頼できる情報かどうか」を常に見極めようとしています。そのためには「この情報を発信している理由」「根拠となる事実や実績」を記事内で明示することが重要です。特に以下のような工夫を取り入れることで、専門性や信頼性が高まります。
- 筆者の経験や知識の背景を、冒頭やプロフィールで補足する
- 引用元の明示や、一次情報へのリンクを掲載する
- 実績・データ・事例に基づいた根拠の提示を行う
難易度:中(3ヶ月以内)
サイトの更新日・記事の著者名を表示する
Googleは「いつ書かれた情報か」「誰が書いた情報か」を重要視しています。特に専門性(Expertise)や信頼性(Trust)を評価する上で、記事の鮮度と発信者の明確さは非常に重要です。
- 記事ページに「公開日」「最終更新日」を表示する
- 著者の名前を記載し、プロフィールページへのリンクをつける
- 専門性を示す肩書きや経歴があると、なお効果的
グローバルナビやフッターに信頼情報を設置
ユーザーは、「このサイトは安全か?」「個人情報は守られるのか?」といった視点でもサイトを見ています。信頼できる企業かどうかを判断する材料として、法的表示や情報保護に関する案内の有無は非常に重要です。特に以下のような項目は、グローバルナビ(上部メニュー)やフッター(下部エリア)に設置しておくことで、訪問者にもGoogleにも「信頼性がある」と評価されやすくなります。
- プライバシーポリシー
- 特定商取引法に基づく表示
- 利用規約
- お問い合わせページ(フォーム)
読みやすい構成やデザインでユーザビリティを高める
どんなに良い情報でも「読みづらい」「探しにくい」と感じられた時点でユーザーは離脱してしまいます。Googleはこうしたユーザーの使い勝手(=ユーザビリティ)を重視しており、読みやすさ・わかりやすさを評価しています。
- 見出し(H2・H3など)を適切に使い、情報を整理する
- 箇条書きや、表を使って要点をまとめる
- スマホで読みやすいレイアウトにする
よくある質問(FAQ)や業界の基礎知識ページを充実させる
FAQや基礎知識のページは、訪問者にとっての「入り口」として非常に重要です。SEOの観点でも、「ユーザーの疑問に先回りして答える」姿勢が評価されます。初心者向けに基本から解説するページを用意することで、専門性のアピールにもつながります。
- よくある質問(FAQ)を掲載する
- 悩みを解決するためのブログを用意する
- 「悩み別」「目的別」にナビゲートする構成にする
- 関連リンクを張り、より良い情報提供をする
サイト全体にSSL(https)を導入する
SSLとは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みのこと。httpsで始まるURLはSSLが導入されており、安全な通信が保証されています。今やSSL化は必須。見る人のためにSSL対応は必須です。
- レンタルサーバー会社の無料SSL機能を使用できる
- 導入後は「http→https」へのリダイレクト設定を忘れずに
難易度:高(12ヶ月以内)
クローラビリティを確保する
クローラビリティとは、Googleのロボット(クローラー)があなたのサイトを正しく読み取れる状態のこと。SEOの土台として、まずは検索エンジンに正しく認識されるように整えることが必要です。
- サイトマップ(XML形式)を作成して、Google Search Console に送信する
- モバイル対応(スマホ表示に最適化されたレスポンシブデザイン)を確認する
- 構造化データ(Schema.orgなど)で、ページの内容を明示する
SNSでの話題性や第三者による言及を促す
Googleは「まわりから評価されているか」を重視しています。つまり、どれだけ外部から言及されているかが、権威性の判断材料になります。自分のサイトだけで「良い情報です」と言っても不十分。第三者に紹介されてはじめて、信頼されるサイトとして扱われます。
- SNSでの情報発信をし、話題になる機会をつくる
- 他の専門家・事業者とコラボする関係を構築する
- 外部サイトに寄稿したり、他メディアに紹介される機会を狙う
- 記事にコメントやシェアがつきやすい内容(図解・比較・データなど)にする
メディア掲載実績や公的機関との連携を示す
Googleは「信頼できる情報源かどうか」を判断する際に、社会的に認められているかどうかを重要視します。たとえば、新聞や専門誌、業界メディア、公的機関などから評価・紹介されている実績は、権威性を示す強力な根拠となります。
- メディア掲載実績を掲載する
- 受賞歴などを紹介する
- 公的機関からの認証(資格など)を明記する
- 第三者機関のレビューや比較サイトでの評価を引用する
高品質な被リンクを獲得する
被リンク(外部リンク)は、昔からSEOにおける最重要指標の一つです。ただし現在は「数」よりも「質」が重視されており、信頼性の高いサイトから自然に貼られたリンクが特に評価されます。
- 他サイトに「参考になる」と紹介されるような記事をつくる
- 地域のポータルサイトや業界団体のページに掲載してもらう
- 自社が主催・協力したイベントなどの告知ページにリンクを掲載してもらう
- お客様の声や事例紹介として、他社のブログなどに登場する機会をつくる
- プレスリリースを活用して、報道機関やニュースメディアに露出する
体験ベースの具体的なエピソードや事例を記事に盛り込む
Googleは「リアルな経験に基づいた情報」を重視するようになっています。専門家の知識だけでなく、実際の経験や体験談があると、より信頼されるコンテンツになります。
- 自分の経験や体験談を取り入れる
- クライアント支援の事例や成功ストーリーを紹介する
- 写真や図解などを加えることで、読み手の理解や信頼度もアップする
最新のGoogleアップデートとSEOの今
「以前は上がっていたのに、突然順位が下がった…」
「同じように更新しているのに、なぜ評価されない?」
そんな悩みの背景には、Googleによるアップデートの影響があるかもしれません。
特に近年のGoogleは「ユーザーにとって本当に価値のある情報か」を厳しく見極めるようになっており、検索結果に大きな変化が起きています。
アップデートの傾向①:E-E-A-T重視の強化
Googleは「専門性」「権威性」「信頼性」そして「実体験に基づいた価値」を以前にも増して重視しています。これは特にYMYL(Your Money or Your Life)領域──医療・健康・法律・金融など、人生に大きな影響を与えるジャンルで顕著です。
- 専門家の視点を入れているか?
- 実績や体験に基づいて書かれているか?
- 第三者からも認められているか?
こうした観点がますます重要になっています。
アップデートの傾向②:自動生成コンテンツの取り締まり
ChatGPTなどAIによるコンテンツ生成が普及する中で「内容が薄い」「一次情報がない」ページは上位に上がりにくくなりました。Googleは、機械的に作られた文章や、ただ情報をまとめただけのコンテンツを見抜き、順位を落としています。
逆に、「人間の視点が活かされているコンテンツ」はより評価されるようになっています。
アップデートの傾向③:役に立たない記事の大幅評価ダウン
2023〜2024年にかけては、「ヘルプフルコンテンツアップデート」と呼ばれる大規模な変更が行われました。このアップデートでは「誰の役にも立っていない記事」を徹底的に排除。
- 検索キーワードだけを詰め込んだ記事
- 他サイトの情報を言い換えただけの記事
- 書いた本人の知見や経験がない記事
こういった中身が薄い記事は軒並み順位を落とすようになっています。
今、SEOで本当に必要なこと
これからのSEOで必要なのは、「検索エンジン向け」ではなく**「ユーザーのため」のコンテンツ**です。
- ユーザーが本当に知りたいことは何か?
- 自分だからこそ語れる視点はあるか?
- 信頼される情報発信になっているか?
小手先のテクニックではなく、実直で真摯な発信が、最終的に評価される時代です。
まとめ|SEOはテクニックではなく、信頼の設計である
検索順位は、「小手先のSEOテクニック」だけでは上がりません。
本当に評価されるのは、読み手にとって「役に立つ」「信頼できる」「安心できる」情報を丁寧に届けているサイトです。そしてその根底にあるのは、コンセプトの一貫性、ユーザー目線の設計、そして信頼の積み重ねです。
SEOとは、検索エンジンに向けたテクニックではなく「信頼をどう設計するか」という視点で捉えなおす必要があります。
本記事が、あなたのホームページ改善と検索上位獲得のヒントになれば幸いです。
監修者プロフィール

株式会社WINQ 代表取締役。2019年に株式会社WINQを創業し、小規模事業者向けにローカルSEOやコンセプト設計支援を展開。2023年にはローカルSEO専門会社としてWordPressテーマの開発を開始し、2024年に著書『小さな会社を救うローカルSEOのすべて』を出版。
主な実績
- キーワードマーケティング歴15年
- 「ローカルSEO 東京」で検索1位
- 累計500名以上にホームページ活用術を指導
- 著書がAmazon売れ筋ランキング1位を獲得
- 累計300万キーワード以上の効果を分析
- 美容業界で累計300件以上の成果実績
- 元・国内トップアフィリエイター