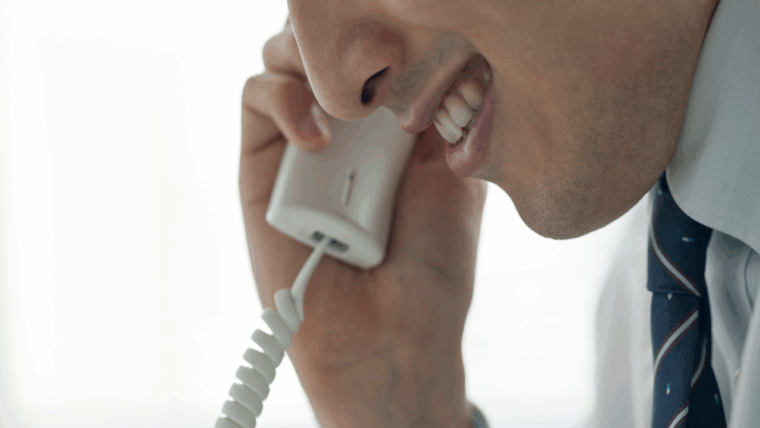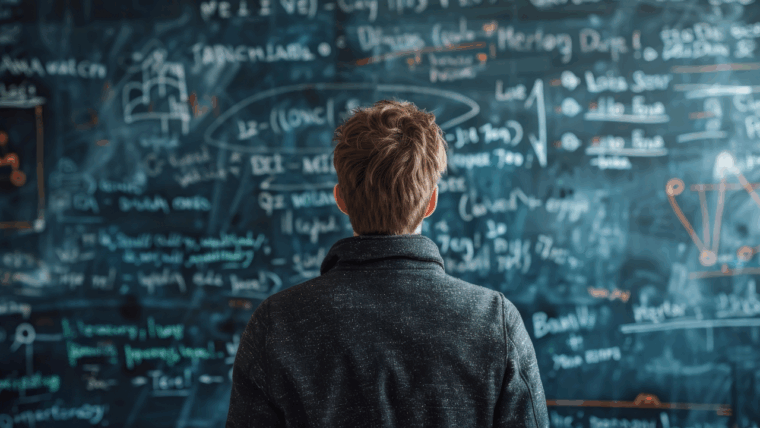「ホームページを作ったのに全然効果が出ない…」
「制作会社に騙された気がする…」
こんな悩みを抱えていませんか?
実は、ホームページ制作で失敗する企業には共通のパターンがあります。この記事では、実際に起こった失敗事例を分析し、あなたが同じ失敗を繰り返さないための具体的な対策をお伝えします。
よくあるホームページ制作の失敗7選
この章では、実際の企業が経験した失敗をもとに、「どこで判断を誤ったのか」「何を見落としていたのか」を具体的に掘り下げていきます。
単なるミスではなく、「なぜそうなったのか」「どうすれば防げたのか」まで分析しているので、自社に置き換えながら読んでみてください。
01
補助金でホームページを作ったが…役に立たない
「補助金が使えるなら、今がチャンスですよね」
そんな流れで、サービス専用サイトの制作を進めたA社。自己負担は約20万円。補助金のおかげでコストは抑えられ、見た目もそれなりに整っていました。
しかし、公開から1か月が経っても問い合わせはゼロ。アクセス数もほとんど伸びず、見に来ているのは既存の取引先ばかりでした。
結局、問い合わせは従来のコーポレートサイト経由に集中。社内では「この新しいサイトって、必要だったのかな…」という空気が流れていました。
問題は「どうやって集客するか」を考えずに作ったこと。
SEO対策も、SNS導線も、広告出稿の計画もありませんでした。「補助金が出るなら、とりあえず今のうちに作ろう」といった軽い判断で、制作だけが先行し、集客の導線設計が抜け落ちていたのです。
このような補助金活用サイトでは、「作った瞬間がピーク」になってしまうケースが少なくありません。
公開後の集客や運用を見据えた設計がなければ、補助金を使って制作したはずのサイトが、結果的に「ムダな支出」で終わってしまうことがあります。
02
デザイン重視で100万円かけたのに…集客ゼロ
「やっぱり見た目って大事だから」
ブランディングに力を入れたいと考えた弁護士のB先生は、デザインに定評のある制作会社に依頼し、約100万円の予算で事務所サイトを制作しました。完成したサイトは非常に洗練されており、同業者からの評判も上々でした。
しかし、公開から半年が経っても、新規の問い合わせは一件もなし。
「見た目は良いけれど、誰にも見られていない」
そんな現実に直面し、B先生は困惑してしまいました。
社内では「名刺代わりになればいい」と自分たちを納得させようとする空気もありましたが、本音では「これで良かったのだろうか」という後悔が残っていました。
問題は「デザインだけ」に全振りしてしまったこと。
SEO対策やコンテンツ設計、導線づくりなど、集客につなげるための仕組みはほとんど手つかずでした。
そして最大の問題は、100万円をどのように回収するかという計画が存在していなかったことです。
「見た目が良い=成果が出る」という誤解は根強いですが、ホームページは見られて初めて意味を持ちます。デザインは目的を果たすための手段に過ぎません。
投資した費用をどう回収するか、そのために何を仕込むかを考えずに進めてしまうと、高額なデジタル名刺で終わってしまうリスクがあるのです。
03
最安値で選んだ制作会社で…低品質サイトが完成
「どこも同じようなことを言ってるし、安いところでいいんじゃない?」
初めてホームページを作ることになったC社は、複数の制作会社から見積もりを取りました。価格帯は30万円から120万円までと幅がありましたが、最も安い30万円の会社に依頼することに。
しかし、完成したサイトを見てみると、デザインは素人っぽく、スマホでも読みづらい。
「もう少し別のパターンも見せてもらえませんか?」とお願いしたところ「デザインは1案のみです。追加で修正をご希望の場合は、別途費用をいただきます」と言われてしまいました。
仕方なくそのまま公開しましたが、社内でも「これ、本当に作って良かったのかな…」という声が上がるようになりました。
問題は「価格だけ」で選んでしまったこと。
見積もりが安いということは、どこかの工程や対応が削られているということです。テンプレート利用、ヒアリングの簡略化、提案内容の少なさ、サポートの薄さ──こうした要素は、事前には見えにくいものです。
また、費用を抑えた分、発注側としても強く要望を出しづらくなってしまい、本来得られたはずのクオリティを自ら下げてしまう結果にもなりかねません。
ホームページ制作は価格勝負ではありません。
「その費用で、成果が出るサイトを作れるのか?」という視点で判断することが大切です。
04
制作会社に丸投げしたら…期待と違うモノになった
「プロにすべて任せた方が、早いはずだ」
そんな考えで、Webに詳しくないD社は制作会社にすべてを任せてホームページを依頼しました。
初回の打ち合わせで大まかな希望を伝えたあとは、進捗を聞く程度。デザインや構成の確認はほとんどしていませんでした。
そして納品直前、上がってきたサイトを見て違和感を覚えます。
カジュアルで親しみやすい雰囲気を求めていたはずなのに、完成したのは堅く無機質な、よくある企業サイト風のデザイン。時間も予算も残っておらず、不本意なまま公開することになってしまいました。
問題は、依頼先を疑わず「プロなら安心」と盲信したこと。
制作会社といっても、ヒアリングから提案まで丁寧に行う会社もあれば、テンプレート通りに進めるだけの会社もあります。
プロだから安心、ではなく、プロにも幅があるということを考えるべきです。本当にいい制作会社ほど、お客様へのヒアリングを入念に行います。
ホームページ制作は、成果を出すための共同作業。自社の目的や価値観を理解してくれる相手を選び、制作過程でもこまめにすり合わせを行うことが、大切です。
05
ホームページは完成したのに、更新できず放置状態
「プロにすべて任せた方が、早いはずだ」
そんな考えで、Webに詳しくないD社は制作会社にすべてを任せてホームページを依頼しました。
初回の打ち合わせで大まかな希望を伝えたあとは、進捗を聞く程度。デザインや構成の確認はほとんどしていませんでした。
そして納品直前、上がってきたサイトを見て違和感を覚えます。
カジュアルで親しみやすい雰囲気を求めていたはずなのに、完成したのは堅く無機質な、よくある企業サイト風のデザイン。時間も予算も残っておらず、不本意なまま公開することになってしまいました。
問題は、依頼先を疑わず「プロなら安心」と盲信したこと。
制作会社といっても、ヒアリングから提案まで丁寧に行う会社もあれば、テンプレート通りに進めるだけの会社もあります。
プロだから安心、ではなく、プロにも幅があるということを考えるべきです。本当にいい制作会社ほど、お客様へのヒアリングを入念に行います。
ホームページ制作は、成果を出すための共同作業。自社の目的や価値観を理解してくれる相手を選び、制作過程でもこまめにすり合わせを行うことが、大切です。
06
フリーランスに依頼したら、途中で連絡が取れなくなった
F社はコストを抑えるため、制作実績のあるフリーランスにホームページ制作を依頼しました。
最初の打ち合わせはスムーズで、デザインの初稿までは順調に進行。
ところが、途中から返信が2〜3日遅れるようになり、最終的にはまったく連絡が取れない状態に。納期直前だったため、プロジェクトは一旦中止せざるを得なくなりました。
社内では「結局、時間もお金も無駄になってしまった」と落胆の声が広がり、上司への報告にも苦労したそうです。
問題は、個人事業主に頼んでしまったこと。
フリーランスは、複数の案件を並行して受けていることが多く、急なトラブルや体調不良、家庭の事情などで業務が止まってしまうことも少なくありません。法人のような代替体制がないため、本人が動けなくなればそのままプロジェクトも止まってしまうのです。
もちろん、すべてのフリーランスが危険というわけではありません。とはいえ依頼前に「途中で連絡が取れなくなったらどうするか?」といったリスクヘッジをしておくことが大切です。
納期や対応範囲、連絡手段について事前にルールを明確にしておくことで、万一のトラブルを防ぎやすくなります。。
07
社員全員の意見を聞いた結果、ホームページがまとまらない
「せっかく作るなら、みんなが納得するホームページにしたい」
そう考えたG社の社長は、原稿の文言やデザイン案について、社員全員に意見を求めるようにしました。
最初は活発な意見交換がされていましたが、次第に方向性がバラバラになっていき、話がまとまらなくなりました。
「この写真、ちょっと堅すぎない?」「もう少し親しみやすい色にしたい」「このサービス、別ページに分けた方がいいんじゃ…」
誰かが納得すれば、別の誰かが不満に思う。
結果、制作の打ち合わせが毎回やり直しとなり、公開時期もどんどん後ろ倒しに。
問題は「全員の納得」を目的にしたこと
ホームページの役割は、社内の満足を得ることではなく、社外のお客様に伝えることです。
特に小規模企業では、制作担当が曖昧なまま「みんなで決めよう」とすると、誰も責任を取らず、話がループする状態に陥りがちです。
意見を集めるのは良いことですが「最終的な意思決定者を決めておく」「意見の反映は目的に沿うものだけに絞る」などの線引きが必要です。
ホームページは社内の作品ではなく、特定の目的を果たすための営業ツールであることを忘れないようにしましょう。
失敗の根本原因は「3つの段階」がある
ホームページ制作で失敗する企業の多くは、同じような原因でつまずいています。
表面的には「問い合わせが来ない」「業者と揉めた」といった悩みに見えても、その根本には、共通する3つの段階での準備不足があります。
この章では、「計画」「制作」「運用」それぞれの段階で起こりやすい代表的な失敗を解説します。
【1】計画段階の失敗
目的・ターゲットの設定不足
「とりあえずホームページが必要だと思って…」という動機でスタートすると、伝えるべきことが定まらず、誰にも響かないサイトになってしまいます。目的が曖昧なまま作ると、成果が測れず改善もできません。
集客戦略の欠如
「作れば見てもらえる」と思っていませんか?実際には、SEO、広告、SNS、口コミなど、訪問者を集める“導線”がなければ誰も来てくれません。集客は制作前から設計すべき“最重要項目”です。
予算・相場の把握不足
相場を知らないまま進めると、安かろう悪かろうに引っかかったり、逆に無駄に高額な契約をしてしまうことも。「何に、どこまでお金がかかるか」を事前に把握しておくことが必要です。
【2】制作段階の失敗
制作会社選びのミス
「紹介されたから」「人柄が良さそうだったから」だけで選んでいませんか?重要なのは、作ることでなく「成果に導く知見があるか」です。ホームページを「使える形」にしてくれるパートナーかを見極めましょう。
コミュニケーション不足
丸投げすると意図が伝わらず、過度に干渉すれば制作側が疲弊し、どちらでも認識のズレが発生します。成果を出すには、お互いが“目的と役割”を理解したうえでの対話が必要です。
契約条件の軽視
「何回まで修正できるの?」「納品後に手直しできるの?」など、細かい契約条件を確認しないまま始めると、後でトラブルになります。とくにリース契約には注意が必要です。
【3】運用段階の失敗
技術面の軽視
スマホで崩れる、読み込みが遅い、SSLが未設定…など、基本的な技術面を軽視すると、ユーザーからの信頼を失います。また、Googleの検索評価にも大きく影響します。
ユーザビリティの無視
せっかく来てくれても、問い合わせフォームが使いにくかったり、導線が分かりづらければすぐに離脱されます。ユーザーの立場で設計されたサイトであることが必須です。
継続的な改善不足
公開して満足し、数年間ほぼ更新されない…そんなホームページは検索順位も落ち、存在感が消えていきます。運用・改善の体制を前提に設計することが、成果への近道です。
段階別!ホームページ制作の具体的な対策
ホームページ制作を「うまくいく投資」に変えるには、制作前・制作中・運用後のすべてのフェーズで、意識的に対策を打っておくことが大切です。
ここでは、失敗しないために“最低限押さえておくべきチェックポイント”を、段階ごとに紹介します。
【1】計画段階でやるべきこと
ホームページの目的を1つに絞る
「認知を広げたい」「採用強化したい」「問い合わせを増やしたい」など、目的が曖昧だと構成もデザインもブレます。ひとつの目的に絞って設計することで、訪問者に伝わるサイトになります。
ターゲットを具体的に想定する
誰に見てほしいのか?その人は何に困っていて、何を求めているのか?実在の顧客像をもとに、サイト構成や導線を考えることが重要です。
集客の流れを事前に描いておく
Google検索から来てもらうのか、SNSか、チラシか。「どこで出会って、どう誘導するか」を描いてから制作することで、成果につながる設計になります。
制作費だけでなく、集客・運用費も含めて予算を組む
「見積もりが安い=お得」ではありません。制作後の広告費やメンテナンス、改善費用を含めて予算を立てましょう。
【2】制作段階でやるべきこと
制作会社の「得意分野」と「実績」を見る
たとえば「デザインに強い」「SEOに強い」「採用サイトに強い」など、会社によって強みは違います。自分の目的に合った制作会社を選ぶことが、成果に直結します。
契約前に、見積書・仕様書・スケジュールをしっかり確認
- どこまでが含まれていて、どこからが追加料金なのか
- 修正は何回までか
- 誰が何をいつまでにやるのか
曖昧なまま契約すると、後からトラブルになります。
コミュニケーションのスタンスを整える
完全丸投げでも、全部自分でやるつもりでも、うまくいきません。目的と優先順位、判断基準を伝えることが、良い制作物への近道です。
【3】運用段階でやるべきこと
スマホ対応・表示速度・基本的なSEOは必須
技術的な土台が弱いと、せっかくのデザインも無駄になります。スマホで見やすいか、ページの読み込みが遅くないか、検索に出るか。この3つは必ず確認しましょう。
問い合わせフォームは極力シンプルに
フォームの項目数が多すぎたり、わかりにくい設計になっていたりすると、離脱の原因になります。名前・連絡先・相談内容だけでも十分問い合わせは成立します。
作って終わりにしない。最低でも月1回は改善・更新
会社の活動が変われば、掲載内容もアップデートすべきです。ブログやお知らせを更新するだけでも、Googleからの評価は高まります。
失敗を防ぐ15のチェックリスト
ここでは、ホームページ制作でありがちな失敗を防ぐために、事前に確認しておきたい15のチェック項目を紹介します。
制作前・制作中・制作後の3段階に分けて、自社の状況に照らし合わせながらチェックしてみてください。このチェックリストを使えば、「なんとなく進めて後悔する」を防げます。
【制作前】目的と設計のチェック
- このホームページで「何を達成したいか」が明確になっている
- ターゲットとする顧客像が具体的に描けている
- どこから人を集めるか(集客チャネル)を決めている
- 他社サイトを見て「好き・嫌い」「やりたい・やりたくない」が整理されている
- 制作だけでなく、運用・改善も含めた予算設計になっている
【制作中】依頼とやりとりのチェック
- 制作会社の強みや実績が、自社の目的に合っている
- 契約前に、見積書や仕様書の内容を丁寧に確認した
- 修正の回数・範囲・納期について明文化されている
- 担当者とのやりとりがスムーズで、不明点にすぐ対応してもらえる
- 自社として「目的・優先順位・判断基準」を制作側に伝えている
【運用後】公開後の活用チェック
- スマホやタブレットでの表示が崩れていない
- ページの表示速度がストレスなく見られるレベル
- 問い合わせフォームが簡潔で使いやすい
- 検索結果にきちんと表示されている(=インデックスされている)
- 公開後も月1回以上、更新や改善をしている
第5章|すでに失敗してしまった場合の対処法
ホームページ制作で失敗してしまった…。
でも、安心してください。失敗には必ずやり直す余地があります。
この章では、すでに公開したホームページに効果が出ていない場合に、何をどう見直すべきか、段階別に対処法をまとめました。
ステップ①|現状の課題を冷静に整理する
まずは感情的にならず「どこでつまずいているのか」を洗い出すことが先決です。
以下の視点からチェックしましょう。
- アクセス数が少ない → そもそも「見られていない」問題(SEO・広告など)
- アクセスはあるが反応がない →「伝わっていない」問題(デザイン・文章・導線など)
- 問い合わせは来るが成約しない →「信頼されていない」問題(実績・見せ方・オファーなど)
Googleアナリティクスやサーチコンソールを使い、数値で可視化できるとベストです。
ステップ②|改善できる部分を整理する
すでにあるホームページを「全部作り直す」のではなく、改善ポイントを絞って対処するのが現実的です。たとえば…
- 表現を見直す(ファーストビュー、キャッチコピー、導線)
- ページ構成を整理する(メニューのわかりやすさ、リンクの貼り方)
- 信頼要素を加える(実績・お客様の声・FAQなど)
- SEO対策を加える(タイトル、見出し、検索ニーズとのズレ)
すべてを一気にやらず、「優先順位」を決めて少しずつ手を加えていくのがコツです。
ステップ③|第三者の視点を借りる
自分たちだけで改善しようとすると、「何がズレているか」に気づきにくいことがあります。そんなときは、第三者の視点(外部コンサル・信頼できる制作パートナー)を入れるのが効果的です。
無料相談や診断サービスを活用することで、今のホームページの課題と改善点を明確にすることができます。
【まとめ】失敗から立ち直ることはできる
ホームページは作ったあとが本番です。
むしろ、公開してから「育てていく」ことの方が重要です。
もし今「うまくいっていない」と感じているなら、それはまだ改善の余地があるということ。
冷静に課題を見つめ、できるところから着実に見直していきましょう。
監修者プロフィール

株式会社WINQ 代表取締役。2019年に株式会社WINQを創業し、小規模事業者向けにローカルSEOやコンセプト設計支援を展開。2023年にはローカルSEO専門会社としてWordPressテーマの開発を開始し、2024年に著書『小さな会社を救うローカルSEOのすべて』を出版。
主な実績
- キーワードマーケティング歴15年
- 「ローカルSEO 東京」で検索1位
- 累計500名以上にホームページ活用術を指導
- 著書がAmazon売れ筋ランキング1位を獲得
- 累計300万キーワード以上の効果を分析
- 美容業界で累計300件以上の成果実績
- 元・国内トップアフィリエイター